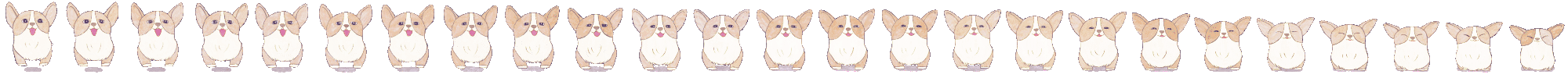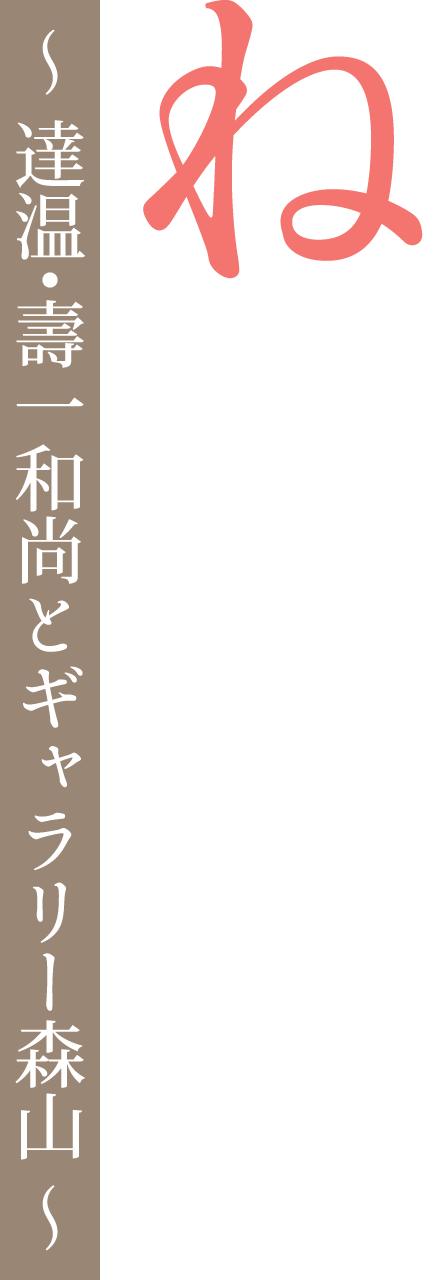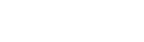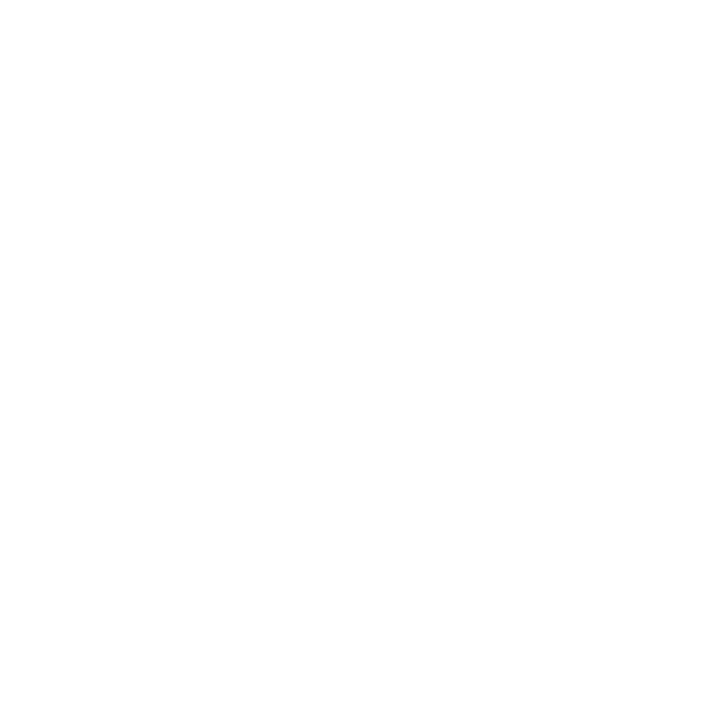
長谷川 達温 - 1
竹森節堂との出会い
その昔、秩父宮殿下が弘前にご滞在になった折、奉納ねぷた大会が開かれました。まだ中学生だったころの達温和尚は、とにかくねぷたが大好きな少年で、仲間たちとともに早速ねぷたをこしらえました。土台はリヤカー、骨組みは裏の墓地に飾ってあった花輪の足、と、ありあわせの材料を組み合わせた手作りでしたが、そのねぷたには、まぎれもない長谷川達温の処女作が、堂々と描かれていたのです。
このようにしてデビューを飾った達温は、上土手町にあった一大小学校の代用教員を経て、戦後、竹森節堂の門を叩きました。節堂は、町絵師の子として弘前に生まれ、上京して蔦谷龍岬、野田九浦といった著名な日本画家に学び、ねぷた絵に狩野派の流れを汲む芸術性を持ち込んだとされる、当代のねぷた絵師の第一人者でした。
節堂のもと、着々と実力を蓄えていった達温は、プロのねぷた絵師として多くの注文をこなす傍ら、弘前公民館のねぷた絵教室の講師を勤めたり、ねぷた絵のハンテンや絵皿、大うちわの商品化に取り組んだりと、名実ともにねぷた絵のホープとして認められるようになりました。
長谷川 達温 - 2
『達温ねぷた』の確立
そんな折、友人にして日本画家でもある福士朋石が、「いくら節堂先生を手本にしても先生を超えることはできないのだから、先生が学んだものを自ら学ぶべきではないのか」と問いかけました。この言葉は、達温の心に大きな波紋を投げかけます。それ以来、東京に通っては古本や掛け軸などを集め、構図や技法を徹底的に研究し、自らの画風の確立に没頭するのでした。
昭和46年(1971年)、達温のもとに一つの仕事が舞い込みます。陸奥新報創刊二十五周年を記念して、棟方志功の絵でねぷたをつくるから、それを手伝ってほしい、というのです。青森が産んだ異能の巨匠、棟方志功の制作の様子を間近で見る機会を得た達温は、そのほとばしる情熱を叩きつけるかのような筆さばきに、大いに感銘を受けました。
やがてそれは、『達温ねぷた』とでもいうべき独自のスタイルに昇華していきます。師・竹森節堂譲りの日本画の芸術性、古い絵画に学んだ伝統、そして棟方志功にヒントを得た津軽の大地を想起させる荒々しく力強いタッチ。以後、達温は、ねぷた絵をけん引する存在として認められ、新聞などのメディアを通してねぷた絵の普及にも努めるようにもなります。
長谷川 達温 - 3
後進の育成と錦絵作家協会
達温は、多くのねぷた絵師を育て上げたことでも知られ、その薫陶を受けた弟子たちは、現在の弘前ねぷたの屋台骨となって活躍しています。ただし、達温は決して手取り足取り教えることはなく、息子の壽一は後年、「突き放したような態度に感じられ、若いころは反発も感じたが、今思えば、上つらを教えるより、分からぬことがあったら自ら調べたり諸兄に教えてもらうことが肝要である、という教え方だった」と述懐しています。
ねぷた絵(弘前・津軽)の話 - 川村岩山
達温和尚の門下となり、ねぷた絵師としてご活躍の川村岩山氏のブログサイトです。
また、錦絵作家協会を設立し、それまで流派間の交流に乏しかったところに風穴を開け、横のつながりを強化しました。その結果、技術や情報の交換が盛んになり、今日に至る弘前ねぷた隆盛の礎を築いたといっても過言ではないでしょう。
快活な見た目とは裏腹に、達温は若いころから病弱で、晩年は入退院を繰り返す日々でしたが、余命三か月と宣告を受けてから実に五年ものあいだ、文字通り骨皮となりながらも、ねぷた絵に執念を燃やし続けました。その姿には、誰しも真に壮絶なものを感ぜずにはいられなかったといいます。自ら「命法衣徒(いのちほいど。「ほいど」は、津軽弁で物乞いの意)」と称し、そのすべてをねぷた絵に捧げつつ、昭和の終わりとともに生涯を閉じました。
巨星、長谷川達温が遺したもの。それは、豪壮華麗なねぷた絵だけではなく、弘前ねぷたを末永く継承してゆくための「人づくり」と「仕組み」、そして、最期の瞬間まで懸命に生き切る「生きざま」だったのかもしれません。
長谷川 壽一 - 1
二代目『ねぷたの和尚』
当寺の住職として、また、ねぷた絵師として達温和尚の跡を継いだのが、三十八世壽一和尚です。壽一は、昭和24年(1949年)に誕生、幼少のころよりねぷた絵に打ち込む父・達温の背中を見て育ち、早くも小学生のころには色付けの手伝いをしていたといいます。
父だけでなく、母・幸子からの影響も少なくありませんでした。幸子は新寺町の法源寺の縁戚で、弘前市長を五期にわたって務めた藤森睿氏の姪にあたりますが、ハイカラ好きな一方、焼き物や絵など美術への関心が高く、そんな幸子の資質が、壽一の感性を育むうえで大きな役割を果たしたことは想像に難くありません。
やがて父から少しずつ仕事を分けてもらうようになり、父子それぞれふすまを隔てて作業に没頭する姿が見受けられるようになりました。ここに、二代目『ねぷたの和尚』としての活躍が幕を開けるのです。
長谷川 壽一 - 2
繊細さが持ち味
達温と壽一は、それぞれの性格の違いがそのままねぷた絵の画風にも反映していたようです。達温が豪放磊落でメディアへの露出にも積極的だったのに比べ、壽一は繊細でこまやか、外へアピールするよりも、自らの世界を徹底して突き詰めるタイプだったといえるでしょう。
壽一のマスコミ嫌いは有名で、父の没後、住職を継いでからのこと。取材依頼の電話が来ると、「はい、ただいま住職に代わりますのでお待ちください」と、まだ年若かった息子(現住職三十九世義高和尚)に受話器を押し付けてしまうこともしばしばだったそうです。
その一方で、骨董を愛で、古美術に学ぶ姿勢は父をしのぐほどで、加えて、洋画を含めた近現代の美術についての造詣を深めていった点において、父・達温と一線を画すといえます。とりわけ、地元愛から青森県出身の作家に関心を寄せ、こぎん刺しから油絵にいたるまで、多くの作品を蒐集しました。
時折おかしみさえ感じさせるこだわりを覗かせながら、古今東西を問わず一途に美術そのものを愛し、己の感性をひたすらに高めていった、長谷川壽一。ねぷた絵を活躍の場としつつ、その視線ははるかに広い地平を見渡していたに違いありません。

長谷川 壽一 - 3
ギャラリー森山
妻の実家である森山家の古民家に手を入れ、ギャラリーとして開設する話が持ち上がりました。永年にわたり壽一が地道にコレクションしてきた作品を、少しでも多くの人に見ていただき、また、青森県出身の作家をもっと広く知ってもらうためです。
壽一は寸暇を惜しんで準備に精を出し、平成16年4月17日、ついにオープンにこぎつけました。野沢如洋展、関野準一郎展、ねぷた展、鳴海要展、幽霊展と、展覧会を立て続けに開催しましたが、それを見届けるかのように、その年の11月、壽一は五十五歳の若さでこの世を旅立ちました。
壽一が遺した、この『ギャラリー森山』のコンセプトは、「気兼ねなくご来場いただき、お茶でも飲みながら、作品を味わい、青森県が生んだ美術家たちに想いを馳せてほしい」という、「喫茶去」の精神です。ちょっと一服、のつもりで、気軽に足を運んでみてはいかがでしょうか。